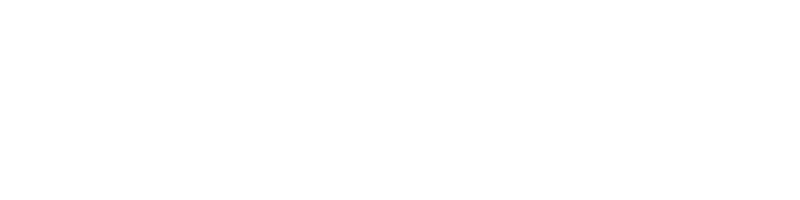【いじめの重大化要因等の分析・検討会議(第1回)】で座長に選任されました
このたび、こども家庭庁・文部科学省による【いじめの重大化要因等の分析・検討会議(第1回)】がこども家庭庁の会議室とオンラインのハイブリッド方式により開催されました。
私は委員として出席し、座長に選任され、会議の進行を担当しました。
会議では、まず、こども家庭庁の吉住支援局長、文部科学省の松坂文部科学戦略官より、開会の挨拶とこの分析・検討会議の趣旨などについて説明がありました。
その概要は以下の通りです。
●令和6年10月31日に公表された文部科学省【令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果】によると、令和5年度の【いじめの重大事態の発生件数】については過去最多の1,306件であることが報告されました。
●このことは極めて憂慮すべき状況が継続していると認識しています。
●このことを受けて、昨年11月8日に【いじめ防止対策に関する関係省庁連絡会議】が開催されました。
その会議では、【いじめ防止対策の更なる強化について】が打ち出され、重大事態調査報告書を活用したいじめの質的分析のための専門家会議による検討が求められていました。
●そのことを踏まえて、このたび有識者の参画を得て、重大事態調査報告書の分析を行い、分析の結果得られたいじめの端緒・予兆や重大化要因等を各学校の設置者及び学校における未然防止等に活用することを目的として、「いじめの重大化要因等の分析・検討会議」を開催されることにしました。
委員は大学教員4名、弁護士1名、学校支援の専門家1名、大学生1名の合計7名です。
第1回は、はじめに、事務局の会議の趣旨・進め方・報告書のイメージ等についての説明の後、委員の皆様の自己紹介及び【いじめの重大化要因等の分析・検討会議】に臨むに当たっての考えなどを共有しました。
そして、分析を担当する子どもの発達科学研究所の所長。副所長より、研究所でのいじめの重大事態調査報告書の分析の進め方の経過の報告を踏まえて、委員が、今後、さらに報告書の分析を進めるうえでの分析の視点や留意点、配慮すべき事項などについて意見交換をしました。
最初の会議の2時間は、各委員の御経験と知見を踏まえた、分析の視点・論点・留意点に関する率直な意見交換が進みました。
会議後に、大学4年生の村宮委員とさらに懇談のひと時を持ちました。
村宮さんは、小学生・中学生・高校生に最も身近な年齢の1人であるとともに、大学でまちづくりの学びを深めつつ、探求型学習支援の実践をしている経験を活かして、いじめの当事者の想いをくみ取りながら、委員の役割を果たしたいと語ります。
私も20代の学生の頃に、初めて住んでいる三鷹市の「まちづくり市民会議」の学生代表委員をつとめて、その意見の反映を経験したことをお伝えして、ぜひ、この機会を生かして、重大事態の要因分析に向けて、決して遠慮することなく、積極的に参画してほしいと話しました。
本分析・検討会議は、いじめの重大事態という生命と人権に関わる深刻な課題への取り組みですので、2人とも大変に緊張して会議に臨みました。
そこで、会議後の対話を通して、ようやく笑顔で写真を撮ることができました。
私は、文部科学省・こども家庭庁共管の【いじめ防止対策協議会】委員として、昨年8月30日に公表され・全国の自治体に通知された【いじめの重大事態の調査に関するガイドラインの改訂】に参画しました。
市長としての経験や、この取組みに参画した経験等を生かして、ぜひ、多世代で、幅広い分野の有識者で構成される委員の皆様とご一緒に、誠心誠意、分析・検討会議の座長としての責務を果たす決意です。


 清原慶子 Official Website
清原慶子 Official Website