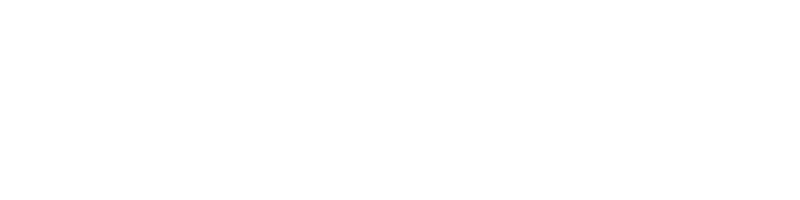【地域コミュニティ】の交流の大切さ
年に2回の開催が恒例の、新川中原住民協議会・新川中原地区災害対策連合会共催の【町会・自治会代表と住協・災対連の懇談会】に出席しました。
新川中原地域の住民としてこの懇談会があることは、住民協議会報の記事などで承知していましたが、実際に参加することになったのは、地域ケアネットワーク新川中原の副代表の1人として、畑谷代表と一緒に来賓として招かれるようになってからのことです。
「コロナ禍を経て、【ソーシャル ディスタンス】という言葉によって、人との接触を避ける傾向が広まり、地域行事の開催が回避され【地域コミュニティ活動】が困難に直面してきました。
【住民協議会】の畝尾会長は、開会あいさつで「地域の交流は重要であり、率直な対話を」と呼びかけました。
【災対連】の麻生会長は、「今年の11月には総合防災訓練のメイン会場が新川中原地域となることから、ぜひ、皆さんのご参加を」と呼びかけました。
来賓あいさつで、【丸池の里わくわく村】の海老沢村長は、「丸池の差との中にある4枚の水田を、エリア内の4校の小学校5年生が田植えをして稲刈りをするまで、日常的に雀などの被害から守っているところ、近年は雀が減って、少し気が抜けている」という自然の変化を語りました。
【ケアネットしんなか】の畑谷代表は、1月のサロンで参加者が1つの文字の書初めをしたところ、「元」「健」が多かったことにわかるように「元気」「健康」は地域住民の大切な目標であることがわかると紹介しました。
私は、夏休みにはサロンに小学生が参加するなど、多世代交流がみられることをはじめ、ケアネットでは、来年度の継続目標を【多世代交流の幸せを実感できる活動をする】とするとともに、単年度目標を【ケアネットに関わる人の人生を豊かにする】というような内容にしようと考えていることを紹介して、町会自治会の皆様の事業への参加を呼びかけました。
地元の鷹南学園副学園長で市立第五中学校の櫻井校長、コミュニティスクール委員会の吉田会長も参加しています。
議事ではまずは、【住民協議会】や【災対連】の今年度の活動報告や来年度の事業計画を共有しました。
そして、地域内の16の町会自治会の内、参加された12名の方々の活動報告や情報交換が行われました。
加盟世帯が約600世帯の町会があれば、約40世帯の町会もあります。
盆踊り、防災訓練をする町会・自治会があるとともに、日常的な情報交換や清掃活動による安否確認や声がけなどのつながりも大切にされています。
役員の任期が1年という町会も少なくなくて、若い世代を含む多くの方が役員の役割を経験するメリットもありますが、継続的な事業等を十分に実施できないという課題も発言されました。
ある町会は他の地域団体との連携事業が【三鷹市がんばる地域応援プロジェクト】に採択され、その補助金を活用して新規事業を立ち上げたことを報告しました。
これは私が市長在任中に創設した町会自治会活性化プロジェクトであり、この地域でも活用されたことを幸いに思いました。
会議後に、これも恒例の全員写真を撮影しましたが、私は地域コミュニティの活動を支える皆さんの集合写真に加わることができて、本当に光栄に思います。
その後、ある町会の会長であるとともに、毎週金曜日に開催の【しんなかコミュニティカフェ】を、ケアネットの畑谷代表とともに運営されている羽鳥さんのコーディネートによる多彩な手作りのお料理を囲んで、懇親の機会がもたれました。
正式な会議とは別に、この懇親会でも、参加者が率直に多様な話題を語り合っています。
前市長である私にも、同じ地域に住まう仲間として、深刻な地域課題について意見を求める方もいて、その信頼が、本当にありがたいです。
これも、この場に手作りのお料理があることによる効果ではないかと感じました。
地域コミュニティには、家庭・職場・学校とは別の、住民にとっての【第三の居場所】がみつかる可能性があります。
そして、1人ひとりの【家事・仕事以外の活躍の場所】【愚痴や悩みを言える場所】【地域課題の発見と解決の糸口】がみつかる可能性があります。
こうした可能性を増やしていくために、このような【交流の場】が確かに機能していると感じます。



 清原慶子 Official Website
清原慶子 Official Website