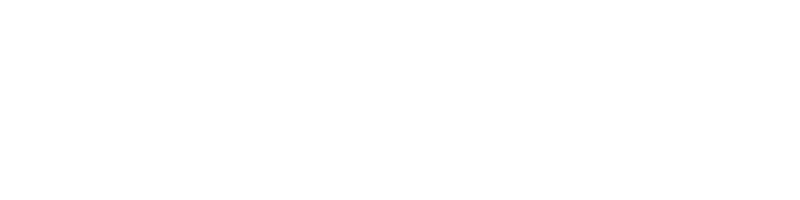文部科学省【第12期中央教育審議会】の最後の総会で、あべ俊子文部科学大臣と対話しました
文部科学省第一講堂で、【第141回中央教育審議会総会】が開催され、委員として出席しました。
総会には、あべ俊子文部科学大臣、武部新副大臣、金城泰邦大臣政務官が出席されました。
荒瀬克己会長(独立行政法人教職員支援機構理事長)の議事進行により、最初の議題である、2003年10月の【急速な少子化が進行する中での将来社会を見据えた高等教育の在り方について(諮問)】に応える答申案についての審議が行われました。
答申案については、大学分科会長及び高等教育の在り方特別部会長である永田恭介副会長(筑波大学長)を中心とする委員の審議に加えて、158件のパブリックコメントも反映してまとめられました。
伊藤学司高等教育局長及び永田副会長のご説明の後に、審議が行われ、私は以下の主旨の意見を述べました。
〇本答申案のタイトル【我が国の「知の総和」向上の未来像~高等教育システムの再構築~】に賛同し、その幅広い訴求を期待します。
永田副会長は【少子化答申】ではなく、【知の総和向上答申】と呼びたいと言われましたが、その通りと思います。
〇本答申が示している【目指す未来像・育成する人財像】を実現するためには高等教育機関だけが取組むのではなく、【学修者本位】で進めることと、高等教育機関に閉じるのはなく【幅広いステークホルダーとの協働で推進する体制】が必要です。これについての記述が最終案では付加され、「おわりに」には、「本答申で提言した改革が実行されていく中において、未来の社会を支える学修者が自ら主体的・自律的に学び、多様な価値観を持つ人々と協働して、社会や世界に貢献していくための力を身に付けていくことも一層期待される」と付加されました。
学修者、高等教育で学ぶ人は、高等教育の主体であり、改革の主体であると考えます。
〇このことは、【学修者本位の教育の更なる推進】の中に、【出口における質保証】の促進が明記され、【認証評価制度の見直し】が明示されていることも重要であり、【高等教育の社会的価値】を客観化するために重要な方向性と受け止めます。私が委員を務めている【大学分科会法科大学院等特別委員会】の今期最後の会議でも、【法科大学院制度20年】と同時に【認証評価制度20年】についての取組みが貢献できるとの複数の委員の発言がありましたし、今後の適切な【認証評価制度】の構築が期待されます。
〇私は市長経験者であるとともに地方の私立大学教員の経験もあることから、本答申が高等教育の価値と使命を果たすうえで、「地方」や「地域」の視点を重視していることは有意義です。
たとえば、【地域連携プラットフォーム】の仕組みを発展させ、各地域の高等教育を取り巻く状況や課題、将来の人材需要等を地域の高等教育機関が共通に認識し、地方公共団体や産業界等地域の関係者も一体となって具体的な取組に向かうことができる場の構築が重要であり、各地域で実効性のある取組を推進するための協議体【地域構想推進プラットフォーム ( 仮称)】を構築することが必要であるとの提起は重要です。
さらに【地域構想推進プラットフォーム(仮称)】の議論を経て、【地域研究教育連携推進機構(仮称)】の取組へ発展することや、相互に連携することを通じて、地域における議論や大学等間の連携が活性化することが期待されます。
〇文部科学省では来年度に【地域大学振興室】を新設することが予定されていることから、今後の政策パッケージでは、【地域大学振興室】がコーディネーターとなって、ぜひ、都道府県・市区町村(自治体)との連携によってこの構想を実現し、推進することを期待します。国立大学の【地域の高等教育機関のけん引役】としての機能強化についても記載されていることから、ぜひ、全国の地方・地域の実情に応じて、適切な高等教育機関の配置とその機能が発揮できる条件整備を、高等教育機関、国、自治体、産業界等との連携の中で推進していただきたい。
そして、数人の委員の発言を経て、答申案が可決され、荒瀬会長、永田副会長からあべ俊子文部科学大臣に手交されました。
あべ大臣は、答申を受けられてから、次のような主旨のあいさつをされました。
〇1年5か月にわたる委員の英知を結集した審議による充実した内容の答申に感謝します。
〇急速な少子化が進む中で将来社会を見据えた高等教育の在り方についての提言と受け止めます。
〇本答申をしっかりと受け止めて、必要な制度改革を含めて課題解決に向けて全力で取り組んでいきたいと思います。
〇本日は第12期審議会の最終の総会であり、2年間のご尽力に感謝します。この2年間の他の答申も含めて、文部科学行政を前に進めて行きたいです。
その後、2つ目の議題である【第12期中央教育審議会の審議の状況について】、生涯学習分科会、初等中等教育分科会、大学分科会のそれぞれを担当する局長から概要説明があり、そののち、各分科会長が発言しました。
私は生涯学習分科会長として、第12期を振り返り、特に「社会教育人材」特別部会の取組や、2024年6月の【地域コミュニティの基盤を支える今後の社会教育の在り方と推進方策について(諮問)】に応えるために「社会教育の在り方特別部会」での闊達な審議を進めている状況を報告しました。
初等中等教育分科会長を務められた荒瀬会長からは、会長としての今期最後のあいさつとして、全国高等学校長協会会長石崎規生先生が発信された【教育へのレスペクトを取り戻す】というメッセージを共感をもって紹介されました。
すなわち、人財こそが唯一の資源であると言われる日本が、対症療法的な教育改革にとどまらず、教育を最も大切なものとし、必要な投資を惜しまないといった【教育へのリスペクト】を今一度社会全体で共有されていくことが必要なのではないかというメッセージです。
この日、幸いにも、私はほんの短い時間ではありましたが、あべ俊子文部科学大臣と2人でお話しする機会をいただきました。
あべ大臣は、今、多くの教育をめぐる重要な政策課題に直面していて、どれも決して解決が容易な内容ではないけれども、こどもたちのために、国民のために、大臣として誠心誠意、前へ進めるようにつとめる決意と姿勢を示してくださいました。
私はその姿勢を大変に心強く思うとともに、私自身も大臣の姿勢に励まされて、教育行政にできる限りの貢献をしていきたいとの想いを強くしました。
あべ大臣との対話と、今期最後の総会での荒瀬会長や委員の皆様からのメッセージを受け止めて、【教育へのリスペクト】の意義についての想いを、深く共有することができました。
今、まさに、私たち一人ひとりが、【教育へのリスペクト】を持つことが求められている重要な時機にあることを、しっかりと心に刻みたいと思います。文部科学省

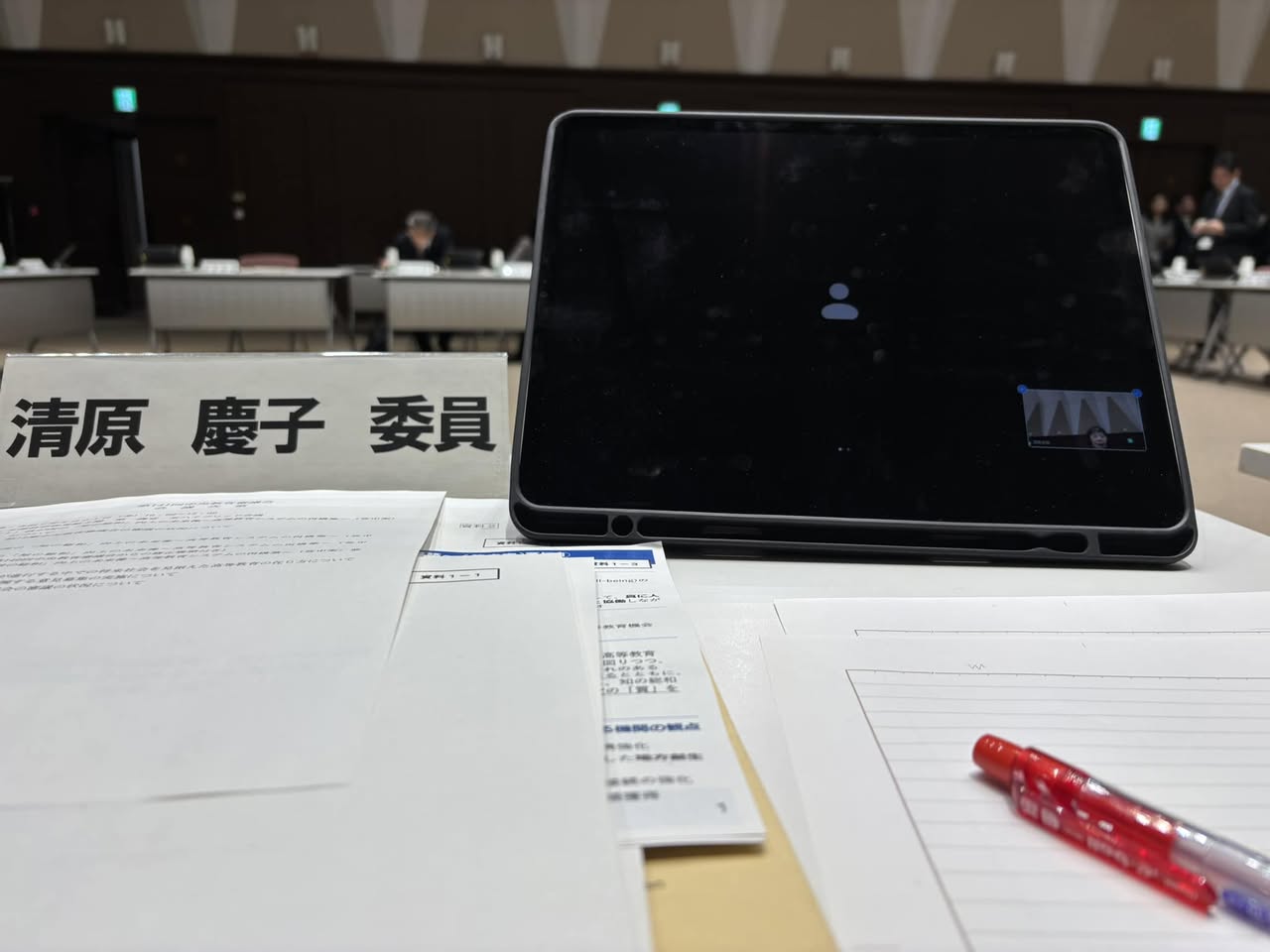
 清原慶子 Official Website
清原慶子 Official Website