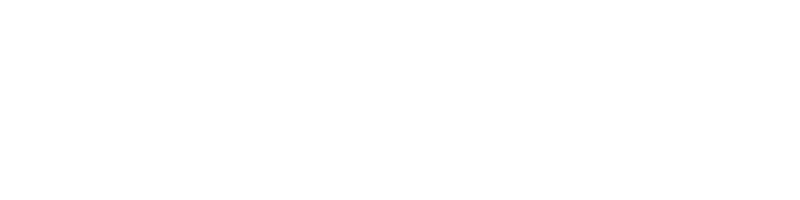会員である【北多摩東地区更生保護女性会】総会に出席しました
会員である【北多摩東地区更生保護女性会】の令和6年度総会に参加しました。
【更生保護女性会】はその活動の目標を、【人間だれもが人として尊重され、自分らしく生きたいと願っています。たとえ、非行や犯罪に陥った人でも同じです。私たちは、まずこれを活動の基本にすえ、一人ひとりが人として尊重される社会を目標とします】として、【同時に社会は、みんなでつくり、みんなで支えあっていくものであり、人と人の連帯なくして成り立ちません。私たちは、人間尊重と、お互いに他を思いあい、連帯しながら、だれもが心豊かに生きられる明るい社会づくりをめざします】としています。
北多摩東地区は、武蔵野市、三鷹市、小金井市、国分寺市の4つの分区をエリアとしています。
会員には、保護司、民生・児童委員の方が少なくはありません。
私は、三鷹市長時代から一人の会員となり、市長在任中は、総会には来賓として招待され、祝辞をする機会を重ねてきました。
そうしたご縁もあり、市長退任後も、1人の会員として参加してきました。
ただ、退任直後にコロナ禍に入り、総会や諸活動は人数制限をしていたことから、この日、総会に参加するのは市長退任後初めてとなります。
総会は、会長の小金井分区の高木和子さんの挨拶から始まりました。高木さんは、「社会が激動する中で、更生保護の取組みが困難に直面していることから、改めて【地域力】が必要であり、身近な手の届くところに心を配ることに力を注ぎたい」と発言されました。
来賓のお1人である東京保護観察所立川支部長の土公千鶴さんは、「児童虐待・不登校・いじめ・孤独・孤立の問題が増加する中にあって、関係団体が連携するとともに、更生保護のボランティア活動についてもっと地域社会に周知する必要性がある」ことを話されました。
その後、正副議長が選出され、2023年度の活動報告・収支決算報告等が可決され、2024年度の役員改選が可決され、新たに会長には国分寺分区の長谷部豊子さんが就任しました。
そして、2024年度の活動計画と収支予算が可決されました。
会場には、三鷹分区保護司会分区長の須藤さんや、同じく保護司の三橋さんも参加されていて、久しぶりの大人数での総会に出席した記念の写真を撮りました。
他にも三鷹分区から多くの会員が参加していました。
さて、この総会に参加して、私と更生保護の関係についても、改めて振り返る機会を得ることができました。
私は、大学教員時代に法務省『人権擁護審議会』の委員を務めたり、市長になってからも引き続き政府司法制度改革本部の「裁判員制度・刑事検討会』『公的弁護検討会』の委員を務めたことから、更生保護の重要性も認識しており、保護司会、更生保護女性会、民生・児童委員協議会などの皆様との対話の時間の確保に努めていました。
そこで、市長就任1期目の2005年に法務省保護局から依頼があり、【更生保護のあり方を考える有識者会議】の委員になりました。この会議の目的は、「治安の回復が大きな社会問題となっている中,保護観察対象者による重大再犯事件が相次いだことを契機として,保護観察の実効性に厳しい目が向けられています。このような状況において,国民の期待に応える更生保護を実現するためには,幅広い観点から更生保護制度全般について検討することが必要ですので,様々な分野の有識者から構成される会議を立ち上げ,更生保護のあり方について議論していただくことにしたものです」とされています。
委員の構成は座長:野沢太三さん(社団法人日中科学技術文化センター会長・元法務大臣)、座長代理:金平輝子さん(日本司法支援センター理事長・日本更生保護女性連盟会長・元東京都副知事)、委員は、佐伯仁志さん(東京大学法学部教授)、佐藤英彦さん(前警察庁長官)、瀬川晃さん(同志社大学法学部教授)、田中直毅さん(21世紀政策研究所理事長)、堀野紀さん(弁護士)、本江威憙さん(公証人・元最高検察庁公判部長)、桝井成夫さん(前読売新聞東京本社論説委員)と私です。
2005年7月から、2006年6月27日まで18回の会議が重ねられ、『更生保護制度改革の提言~安全・安心のくにづくり・地域づくりを目指して~』という最終報告をめとめました。
そこでは、【更生保護の問題の所在と改革の方向性】として、以下が列挙されました。
(1)更生保護制度の運用についての国民や地域社会の理解が不十分であること:国民・地域社会の理解の拡大
(2)民間に依存した脆弱な保護観察実施体制:官の役割を明確化し,更生保護官署の人的・物的体制を整備することにより,実効性の高い官民協働へ
(3)指導監督・補導援護の両面で十分に機能していない保護観察:保護観察の有効性を高め,更生保護制度の目的を明確化し,保護観察官の意識を改革すること等により,強靭な保護観察の実現へ
そして、【#更生保護】は,犯罪や非行を摘発し,刑罰や保護処分を行う【刑事司法制度】の最終段階を担う重要な一環であり,その改革は【裁判員制度】や行刑改革など一連の刑事司法改革の最後の仕上げであることから、この報告書が,将来にわたり,更生保護が国民の期待にこたえることができるよ
う,更生保護の進むべき道を指し示すものになることを願って、1保護観察の充実強化、2執行猶予者保護観察制度の運用改善等、3仮釈放のあり方の見直し、4担い手のあり方の再構築(官民協働・保護観察官・保護司・更生保護施設・社会復帰のための強力な支援と強靱な保護観察実現のための自立更生促進センター(仮称)構想の推進・更生保護官署における人的・物的体制の大幅な拡充 、5 国民・地域社会の理解の拡大(地方公共団体との連携強化・民間ボランティアによる地域社会におけるネットワークの構築と更生保護の考え方の普及・広報活動の充実等・第三者機関の設置・犯罪被害者等への支援 、6 更生保護制度に関する所要の法整備
そして、この報告を踏まえて、2007年『#更生保護法』が制定されました。
この法律は、「犯罪をした者及び非行のある少年に対し、社会内において適切な処遇を行うことにより、再び犯罪をすることを防ぎ、又はその非行をなくし、これらの者が善良な社会の一員として自立し、改善更生することを助けるとともに、恩赦の適正な運用を図るほか、犯罪予防の活動の促進等を行い、もって、社会を保護し、個人及び公共の福祉を増進すること」を目的としています。
国は、この目的の実現に資する活動であって民間の団体又は個人により自発的に行われるものを促進し、これらの者と連携協力するとともに、更生保護に対する国民の理解を深め、かつ、その協力を得るように努めなければならないとともに、地方公共団体は、前項の活動が地域社会の安全及び住民福祉の向上に寄与するものであることにかんがみ、これに対して必要な協力をすることができるとしています。
さらに国民は、前条の目的を達成するため、その地位と能力に応じた寄与をするように努めなければならない。
また、法務省に【中央更生保護審査会】を置くこととされています。
こうした【更生保護】制度とのご縁から、2007年に【日本更生保護女性連盟】が『更生保護女性会の活動について考える(提言)』をまとめる際のメンバーを務めました、これは「地域の人々に寄り添い、地域の中に更生保護の心を広める」ためにまとめられたものです。
まら、2015年4月に【日本更生保護女性連盟】が結成50周年を迎えるにあたり、講演や記念誌発行への協力をさせていただきました。
2019年1月には【北多摩東保護司会2019年初春研修】に講師として招かれ、「更生保護と行政の関わり~支え合う地域のチカラ~」と題してお話をしました。
その年の7月には、東京更生保護女性連盟主催「第69回社会を明るくする運動」講演会で、「支えあい、共に輝き、その先へ~少子化時代の子どもたちをめぐる状況と健やかな育ちの為に何が必要かを考える~」と題して講演しました。
その際には、保護司会、更生保護女性会の三鷹分区のメンバーが応援に駆けつけていただき、大変に心強く思いました。
犯罪の多様化の中で、更生保護の取組みが、地域社会における行政と民間の協働及び各組織の連携の推進によって、何よりも当事者の更生と再犯防止に有意義に働くことを願っています。


 清原慶子 Official Website
清原慶子 Official Website